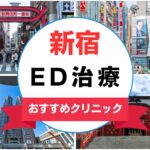男性の不妊や精子に関する悩みや疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。
不妊症の原因は女性だけでなく、男性側にもさまざまな要因が存在し、生活習慣や疾患、射精や精巣の機能低下が影響する場合もあります。
不妊治療は医療機関での適切な検査や診断、治療によって症状の改善や妊娠への道を開くことが可能です。
この記事では、男性不妊になりやすい人の特徴やよくある原因、検査や治療方法などを詳しく解説します。
不妊の主なケースや特徴を知り、早めの受診や対策を取ることで健康被害や症状の悪化を防ぐことが可能です。
悩みを感じている方に具体的かつ最新の研究・医療情報をお届けします。
- 男性不妊症とは?
- 男性不妊になりやすい人の特徴
- 男性不妊の種類と原因
- 男性不妊の検査方法
- 男性不妊のセルフチェック方法
目次
男性不妊症とは?

男性不妊症とは、パートナーと避妊せずに一年間継続的に性交渉を行っても妊娠しなせず、男性側に明らかな原因が認められる状態を指します。
主な原因には精索静脈瘤や精路通過障害、性機能障害があり、精巣や精子の機能低下や精子の通過障害、射精の障害など多岐にわたります。
精索静脈瘤は精巣周囲の静脈が拡張し、血液の逆流が生じて精巣の温度が上昇しやすくなる疾患で、男性不妊のもっとも多い原因の一つです。
精路通過障害や射精障害も妊娠の妨げとなるケースが多いです。
不妊に悩む場合は男性不妊の可能性を念頭に置いて、早期に検査・診断・治療を検討することが自身やパートナーの将来にとって重要となります。
治療には保険が適応される
男性の不妊治療においては、多くの治療や検査が保険適用となっています。
2022年4月の制度改正により、
- 精液の状態を改善する薬物療法
- ED(勃起障害)治療薬
- 無精子症
- 射精障害
- 重度の逆行性射精に対する睾丸からの精子採取手術
など、多様な医療行為が保険適用の対象に加わりました。
こうした治療のうち、スクリーニング検査だけは保険適用外ですが、それ以外の検査や治療法は経済的な負担が減り、患者が積極的に治療に取り組みやすくなっています。
手術となる場合は、公的医療保険の他に民間医療保険も利用可能な場合があり、選択肢も広がっています。
保険が適応されることで、患者が早期に適切な医師の診察を受け、体外受精や顕微授精など高度な治療にもスムーズに進めるのが大きな利点です。
個々の費用や具体的な内容は医療機関や診療機関へ直接相談し、疑問点があれば医師や専門クリニックへ問い合わせてください。
男性不妊になりやすい人の特徴

男性不妊のリスクが高い特徴については、さまざまな側面があります。
これから、見た目、手術歴や病歴、生活習慣ごとに男性不妊になりやすい特徴をご紹介していきますので、該当する点がある場合は早期の医療相談をおすすめします。
【見た目編】男性不妊になりやすい人の特徴
男性不妊になりやすい人には、見た目にも共通した特徴が見られることがあります。
- 睾丸が小さい
- 睾丸が柔らかくて張りがない
- 陰嚢の表面に欠陥が多い
- 睾丸の位置が陰嚢内の上方や鼠径部にある
例えば、睾丸が小さい、柔らかくて張りが感じられない、などの精巣の異常があげられます。
また、陰嚢の表面に血管が多く浮き出ていたり、でこぼこしている場合も要注意です。
陰嚢の見た目が左右で非対称になっている場合や、睾丸の位置が鼠径部にある、つまり停留精巣の可能性があるケースも男性不妊のリスクにつながります。
さらに、陰嚢の上部に睾丸が位置している場合や、精巣が陰嚢内ではなく鼠径部付近に触れる場合も正常な精巣機能の妨げとなりやすいです。
こういった外見的な特徴が見られる場合、精索静脈瘤や精巣の発育不全、精子の質や運動性の低下といった疾患のサインである可能性も高いため、自覚がある方は早めの医療機関受診を推奨します。
【手術歴・病歴編】男性不妊になりやすい人の特徴
手術歴や病歴をもつ男性には、特定の医療イベントが将来的な不妊リスクにつながる場合があります。
- 鼠経ヘルニアの手術を受けた
- おたふくかぜで精巣炎になった
- 抗がん剤治療や放射線治療を受けたことがある
たとえば、幼少期や成人後に鼠径ヘルニアの手術を受けた経験がある場合、手術の影響で精子の通り道が狭くなったり塞がってしまう可能性があります。
また、おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)による精巣炎を発症した場合、精巣組織がダメージを受け、精子を造る機能が低下するケースが知られています。
抗がん剤治療や放射線治療を受けたことのある場合も、精巣や精索など精子の産生や精子の通過経路が障害されるリスクが高いです。
これらの手術歴や病歴のある方は、精液検査や男性ホルモン検査などの医療チェックを受け、自身の生殖機能の状態を定期的に確認することが非常に重要です。
【生活編】男性不妊になりやすい人の特徴
男性不妊のリスクには生活習慣が大きく影響します。
- 睾丸を締め付けるようなズボンを着用している
- サウナを頻繁に利用している
- 長風呂をしている
- 膝の上でPCを置いて作業をすることが多い
- 火を使った調理を仕事としてしている
- 喫煙・飲酒が多い
- ストレスが溜まっている
- 睡眠不足になりやすい
睾丸を強く締め付けるタイトなズボンを日常的に着用している場合、精巣の温度が上昇し、精子の質や数に悪影響を及ぼすことがあります。
また、サウナを頻繁に利用したり、長風呂を好むことで陰嚢の温度が持続的に高くなり、造精機能障害につながるリスクが高くなります。
さらに、膝の上でパソコン作業をする習慣や火を使う調理の仕事も熱による精巣へのダメージを引き起こしかねません。
喫煙や過度の飲酒、慢性的なストレスや睡眠不足も、ホルモンバランス異常や精液の質の低下原因となりやすい生活習慣です。
こうした生活上の特徴がいくつも重なっていると男性不妊のリスクがさらに高まるため、日々の生活習慣を見直すことが将来的な妊娠確率の維持・向上に大切です。
男性不妊の種類と原因

男性不妊にはいくつか種類と原因があります。
ここでは、男性不妊の種類と原因について詳しく解説していきます。
| 原因の種類 | 割合 | 説明(概要) |
|---|---|---|
| 造精機能障害 | 82.4 % | 精子を作る機能の低下(精子数少・運動率低下など) |
| 性機能障害 | 13.5 % | 勃起・射精の問題、逆行性射精など性交機能の障害 |
| 精路通過障害 | 3.9 % | 精子の通り道(精管・射精管など)が閉塞している状態 |
造精機能障害
造精機能障害は、睾丸の機能異常によって精子が正常に作られない状態であり、男性不妊症の約80%を占める最も一般的な原因です。
具体的には、精子がいない(無精子症)、数が極端に少ない、または運動性が悪いなど精子の異常が見られます。
よくある原因に精索静脈瘤があり、これは睾丸上部の血管が拡張して瘤状になることで温度が上昇しやすくなり、精子の質を低下させます。
抗がん剤や放射線治療を受けたケースでも精巣機能の低下が起きることがありますが、多くは原因が特定できない場合です。
年齢を重ねることで造精機能の低下が進行することもあるため、早めに泌尿器科を受診し、適切な診断と治療、生活習慣の見直しやサプリメント・漢方の活用を検討しましょう。
性機能障害
性機能障害は、勃起や射精の働きに問題があり、自然妊娠が難しくなる男性不妊の一種です。
主な原因はED(勃起障害)や射精障害が挙げられます。
EDの場合、十分な硬度の勃起が得られず性交自体が困難になることがあります。
また、射精障害では勃起は可能でも射精ができなかったり精液が膀胱へ逆流する逆行性射精がみられ、これらは糖尿病や手術の影響で発生しやすいです。
心理的要因によるプレッシャーや不適切な自慰行為も一因となる場合があります。
性機能障害は、カウンセリングやホルモン補充療法、人工授精・体外受精など適切な治療を受けることで改善が期待できますので、専門医への相談が重要です。
精路通過障害
精路通過障害は、精子が作られていても射精までの通り道に障害があるため、精子が精液中に現れない状態です。
具体的には精管が生まれつき閉塞していたり、鼠径ヘルニアの手術による影響を受けたり、逆行性射精などが原因になります。
この障害では精液そのものは通常どおり射精されるものの、中に精子が混在しないため、検査を受けるまで気づかないケースも多いです。
早期発見と適切な治療が大切であり、異常を感じた場合は泌尿器科での検査をおすすめします。
男性不妊の検査方法

男性不妊を疑った場合、原因や状態を把握するために多様な検査が行われます。
これから、男性不妊の検査方法について詳しく紹介していきます。
自分やパートナーの健康を確認し妊娠への一歩を踏み出すためにも、早めの検査が役立ちます。
- 精液検査
- 男性ホルモン検査
- クラミジア抗体検査
- 風疹抗体検査
- 感染症検査
精液検査
精液検査は、マスターベーションによって採取した精液を顕微鏡で調べる検査方法です。
精液検査では、
- 精液量
- 精子濃度
- 精子運動率
- 精子の形態
などを総合的に評価します。
同じ男性であっても精液の状態は日々変動するため、検査結果にばらつきが生じることも珍しくありません。
1回の結果が基準を下回っていても、再検査を行うことで正常範囲と判断される場合もあり得ます。
費用については医療機関によって異なり、自治体によって助成制度を利用できる場合もありますので、希望する場合は自治体の制度も積極的に確認するのが賢明です。
男性ホルモン検査
妊娠に向けて不安がある場合、男性も医療機関でのホルモン検査を受けると良いです。
不妊の原因の半数は男性側にもあるといわれ、精子やホルモンの異常が明らかになることも少なくありません。
最近は男性向けのブライダルチェックも盛んに行われており、クリニックによっては精液をご自宅や院内で採取する選択肢も提供しています。
原因を早期に特定し、精子の状態に応じて最適な治療に繋げられるのが大きなメリットです。
情報をもとに妊娠への準備も計画的に進めやすくなりますので、気になる方は積極的な受診をおすすめします。
クラミジア抗体検査
クラミジア抗体検査は、男性不妊の原因となることがあるクラミジア感染の有無を調べるための検査です。
クラミジアは性感染症の一つで自覚症状が少ないため、感染に気づかず放置されることがあります。
その後、精子の通過障害や精巣上体炎を引き起こし、精子の通り道が塞がることで妊娠率を低下させるリスクがあります。
抗体が検出されれば過去や現在の感染履歴が疑われ、必要に応じて追加の検査や治療が行われます。
妊娠を希望しているカップルや不妊が疑われる場合には、女性側だけでなく男性側も積極的にクラミジア抗体検査を受けることが必要です。
検査自体は採血や尿検査で簡単に行えるため、性感染症の予防や早期発見のためにも重要です。
不妊治療の一環として感染症のチェックは大切なステップとなります。
風疹抗体検査
風疹抗体検査は、風疹ウイルスへの免疫があるかどうかを調べるもので、不妊治療や妊娠を目指す夫婦にとって欠かせません。
風疹にかかることで精巣や生殖機能に影響が出ることは稀ですが、妊婦が風疹に感染すると胎児に重篤な障害を引き起こす可能性があります。
男性側が風疹ウイルスの保有者となり、パートナーや周囲に感染を広げるリスクもあるため、妊娠を計画する場合は必ず抗体検査を受けて免疫の有無を確認し、必要ならワクチンを接種しましょう。
感染症検査
男性の不妊検査では、性感染症の有無を確認するための感染症検査が行われます。
- クラミジア
- 淋菌
- 梅毒
- HIV
- B型・C型肝炎
などの検査が代表的で、血液検査や尿検査で実施されます。
これらの感染症は精子の通り道である精管や副睾丸に炎症を起こし、精子の通過障害や運動率低下を引き起こすことは少なくありません。
早期に発見し治療することで、不妊の原因を改善し、パートナーへの感染を防ぐことにもつながります。
男性不妊の治療方法

男性不妊の症状や原因ごとに、最適な治療方法が検討されます。
これから、ホルモン治療や人工授精、体外受精など幅広い治療法について順に解説しますので、ご自身の状態に照らして適切な医療選択肢を考える参考にしてください。
- クロミフェン法
- GnRH療法
- 下垂体ゴナドトロピン療法
- 人工授精
- 体外受精
- 顕微授精
クロミフェン法
クロミフェン法は、男性不妊の中でも特に造精機能障害に用いられる治療方法です。
クロミフェンという薬剤は、脳下垂体に作用して性腺刺激ホルモンの分泌を促進し、精巣での精子産生を活発化させる効果が期待されます。
ホルモン値が正常またはやや低下している男性に適応されることが多く、比較的副作用が少ない点が特徴です。
定期的なホルモン検査や精液検査と併用しながら、医師の判断で投与期間や投与量を調節していきます。
成果が見られない場合は、次の治療選択肢が検討されます。
GnRH療法
GnRH療法は、視床下部性もしくは下垂体性のホルモン分泌異常が原因で発生する男性不妊に対して行われます。
GnRHは生殖ホルモンであるFSH、LHの分泌を促す役割を持ち、定期的な投与により精巣の働きが正常に近づき、精子が作られる可能性が高まります。
重度の無精子症や低ゴナドトロピン性性腺機能低下症に適応される場合が多いです。
治療は専門医のもとで行われ、治療によって十分な量の精子が検出できるケースも増えています。
下垂体ゴナドトロピン療法
下垂体ゴナドトロピン療法は、低ゴナドトロピン性性腺機能低下症と呼ばれる脳の下垂体から分泌される性腺刺激ホルモンが不足し、精巣発育不全や射精障害を引き起こす疾患に対する治療方法です。
精巣の大きさが小さかったり、第二次性徴の遅れ、性機能障害がある場合にホルモン検査で診断が確定します。
この治療ではヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)や卵胞刺激ホルモン(FSH)を注射で補充し、80%前後の患者で精子が確認できるようになると報告されています。
早期の診断と治療介入で妊娠成功率も向上するため、不安がある場合はすみやかに専門医へ相談してください。
当院でホルモン治療ができない場合は、適切な医療機関へご案内します。
人工授精
人工授精は、排卵のタイミングに合わせてカテーテルを使い子宮の入り口から精子を直接子宮内に注入する治療方法です。
採取した精液から状態の良い精子を選別し濃縮して用いるため、
- 精子数がやや少ない軽度乏精子症
- 勃起障害
- 勃起不全(ED)
- 性交障害
- 性感染症
などのリスクがある場合など幅広く適応されます。
精液検査や排卵日の管理と組み合わせて行うので妊娠率の向上が期待できます。
体外受精
体外受精は、女性の卵巣から採取した卵子を体外で精子と受精させ、できた胚を子宮の内膜へ戻す治療法です。
人工授精では妊娠が難しいほど精子濃度が低いケースや、精子運動性が大きく低下している場合に適応されます。
また、精液検査や精子の状態を丁寧に確認しながら進めるため、多くの男性不妊患者で妊娠の可能性が広がります。
最先端の生殖医療技術が駆使された方法であり、専門医療機関で受けることが大切です。
顕微授精
顕微授精は、顕微鏡下で最良の精子を選び、精子をガラス針で直接卵子内へ注入する高度な授精法です。
男性不妊のうち
- 精子濃度が極めて低い場合
- 精子の運動性が著しく悪い場合
- 無精子症で精巣や精巣上体から取得した精子を使う場合
などに効果的です。
重症度の高い男性不妊でも高い確率で受精に至る可能性があるため、体外受精で成果が出なかった場合の選択肢にもなります。
男性不妊かも?と思った時のセルフチェック

男性不妊の可能性が心配な方は、以下のセルフチェックリストをご活用ください。
- 結婚・同居後1年以上、避妊せず妊娠しない
- 精液の量が少ない、または透明でサラサラしている
- 勃起が十分でない、または射精がうまくできない
- 性交の回数が少ない、または途中で中断することが多い
- 睾丸の大きさや硬さに左右差がある
- 睾丸や陰嚢に痛み・違和感・腫れを感じる
- 思春期以降、耳下腺炎(おたふく風邪)にかかったことがある
- タイトな下着や長時間の入浴など、熱がこもる習慣がある
- 喫煙・過度な飲酒・ストレスが多い生活をしている
- 肥満または極端なやせがある
- 長期間、薬の服用や化学物質への暴露がある
上記のチェック項目に該当する場合は、一度泌尿器科や不妊治療を扱う医療機関での検査・診断をおすすめします。
まとめ
男性不妊の大きな特徴は、原因が過去の病気や手術、生活習慣、心因性の場合に加え、原因不明なケースも多い点です。
現在は2022年4月から男性不妊治療も保険適用範囲が大きく広がり、経済的負担が軽減されて高度な医療を受けやすくなりました。
男性不妊が原因の場合、精液検査や専門医の診察によって女性パートナー側の治療方針も大きく変わることから、男女ともに早期の検査が重要です。
不妊治療は夫婦で協力して進めることが成功への近道となります。
最短で妊娠を目指すためにも、男性も積極的に検査や相談を行い、必要に応じて医療機関へ早めにご相談ください。